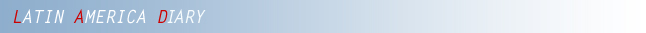その翌日六月一日。私の見果てぬ夢の話を聞いてくれた「エクセルシオ」紙の記者ラウル・セルバンテス・アジャラ氏(本誌「メヒコ航空便」筆者)は、この夜案内してくれた。同席したのは、ほかにカメラマンと私の今後に興味を示してくれたグスタボ・マネージャー。
カリージョは「ラ・メンティーラ」「サボ−ル・ア・ミ」などで知られるシンガー・ソングライターの大流行、こういう人たちがここ数年わが国の音楽レベルをあげてくれたことを大いに喜ぶ私であるが、メヒコでのこの分野の歴史は古く、ラテン・ファンならずとも知っている「ソラメンテ・ウナ・ベス」「グラナダ」の作曲家アグスティン・ララも、自分でピアノを弾き、歌った。シンガー・ソングライターなることばも、その頃にはなく、彼らにとって自作自演は昔から当たり前のことだったのである。
日本では、ラテン歌手といえば、張りのある豊かな声量で情熱的に歌うと思われがちなのは、わが国で売られているレコードが限られているせいもあろうが、この夜のアルバロの歌は、歌手は声に恵まれなくても聴衆を感激させられることを証明してくれた。
巨体に似合わず彼の声は小さく、つぶやくように淡々と歌うが、心にしみ入る。五〇歳を過ぎた年輪のなせるわざが、その曲を作った人にのみ出せる味わいか。この年の大ヒットになった「ラ・メンティーラ(いつわり)」を歌い出した時、客席のあちらこちらから「ノ・ジョーレス(泣くなよ)」とかたわらの恋人を抱きしめる男もいる。
メヒコでは、自分好みの歌が始まったり、歌が佳境に入ると、いっせいにアイ・アイ!と感極まった声が入りみだれ女性(時には男も)は実によく涙を流す。「ノ・ジョーレス」というのも、むしろ掛け声の役目もあり、浪曲や歌舞伎の佳境に入る掛け声にどこか似ていてタイミングがよく、耳というより官能的で音楽を受けとめる感じの彼らが恍惚とした目をステージに向けると、異様でセクシャルな雰囲気さえ漂う。のち、苦しい時も多かったにもかかわらず、私がこの国を去りがたかったのは、何よりもまずこのスリリングなステージをつとめる喜びからであった。また、私はこの時「ラ・メンティーラ」はすべて私の好みに合わせて作られていると思った程で、今でもこの歌を耳にすると涙腺がゆるむ。
頃合を見てアルバロは私を客に紹介し、運よく持っていた彼のヒット曲「ウート・ポコ・マス」の入った私のフォノシート・レコードを私はその場で彼にプレゼント。「サボール・ア・ミ」のイントロが始まると、私にも歌えと彼は促す。臆する私を同席の大男三人が、ウン・ドス・トレス(123)と弾みをつけ、ステージに押し出した。
この偉大なアーティストに遠慮しながら、さり気なくマイクに近づくと、私はいきなり出稼ぎ根性まる出しに、力んで歌った。歌い終えたあと、アルバロが何か言ったのだが、そのことばが分かる程スペイン語が達者でなかった私が、ラウルの説明でアルバロのジョークに一人バカ笑いした時は、客席は甘いボレロにみんなしずまりかえっていた。
その帰途に立ち寄った、名高いマリアッチ広場での流しの歌い手の声量豊かな歌も、アルバロのショウのあとではむなしく聞こえるばかりだった。群集の民族色豊かな装いと、偶然見かけた殺人の現場が、いかにもメヒコ的ではあったが・・・・・

一週間、前期の両記者は、折にふれマスコミでの話題作りに協力してくれ、グスタボ・マネージャーと私はせっせと売り込みに明け暮れた。
常に着物着用を命じられた私は、あまりにも忠実すぎたようである。
橋幸夫の舞台でしか見られないような着物姿の日本人が、毎日九時ごろ、おどおどとホテルを出てくる様子を想像していただきたい。所は、日本なら東京銀座にあたるファレス通り、ホテル前に待ちかまえるタクシーの運転手たちにもあいまいに答え、ホテル横のアメダラ公演にそそくさと消える。名物の靴みがきが声をかけるが、足袋とぞうりにきがつき、黙り込む。公園の反対側の出口から、誰もみていないのを見とどけて、素早く小さな路地にかけこむ。薄汚れた道には、朝から酔っ払いが寄りかかり、よどんだ目で不思議そうに私をみつめる。
その奥の方に、屋根の広い、小型の体育館風の、これも汚れた市場があり、入口では裸足のインディオの女たちが、果物や生きたニワトリなどをならべて客を待っている。
私はカメラを取り出し“俗世界が珍しくてならぬ、やんごとなき人”といった素振りで建物に入り、トリやブタの足などがぶら下がった店々の一角の立食い食堂で御朝食をとる。実はホテルの十分の一くらいの値段ですむからである。
何くわぬ顔でホテルに戻ると、ヒゲの支配人がいんぎんに迎え
「ミスター・ヨシロー、今朝もあなた様のことが新聞に載っていましたが、テレビ出演はいつでございますか?」
とくる。私は逃げるがごとくエレベーターに飛びのるのが常であった。運悪く
ロビーに日本人観光客がいようものなら彼はすっ飛んで行き
「日本から有名なヨシローが来て、当方にご滞在中でございます。もち論みなさまは彼をご存じでしょうね。」
とやすらかだったのだ。

連日の売り込みは一喜一憂の繰り返しで、外国のショウ・ビジネスの厳しさや日本のシステムとの違いも分かってきた。テレビの音楽番組は少なく、日本のように短期間に番組のかけ持ち出演する歌手など皆無である。セ・ケマ(燃えつきて灰になる)といわれ、出すぎても歌手の価値は下がる。
ましてや外国人の私など、最初に出演する番組の価値次第で、その後のランクも決まる。クラブの世界でも同じだ。一般には外国では、ホステスは“夜の女”と考えられているが、ホステスがいなくてショウだけが頼りのクラブでは毎日競って新聞に案内を載せるから、どこに誰が出ているかすぐに分かる。二流クラブに出演でもしようものなら、その後長い間一流の店から敬遠され、出してもらえない。
しかも、そのように新聞の載る案内だけで、地方のクラブでのランクも決まることがあるから、たかがナイトクラブなどと思うことなかれ。
一流と呼ばれるクラブのオフィスは、いつも売り込みの歌手やマネージャーであふれ、日本にも名の知られた歌手の顔が見られる。「アスタ・マニャーナ(明日また)」と、明日に延ばす習慣になれた彼らは、このことばを聞くと、さして気にもとめず、翌日もまたクラブのオフィスに売り込みに来る。
どんな具合か、ある日の風景をご紹介してみると・・・・・・
オーナー「今のショウの評判がよく、延長になりましたので、また来週の木曜にいらして下さい」
一般にメヒコでは金曜日には新しいショウが始まる。二週間単位の契約だが、好評の時は一週間目の木曜日に延長の再契約が交わされるのが通例である。
あっさり立ち上がろうとするグスタボマネージャーに、同じことのくり返しにいい加減厭き頭に来ていた私は彼を引き留め
「残念ですが、来週はロスアンジェルスの仕事があるのですが来られません(心の内を正しく言えば“来週までメヒコ滞在のおカネがないので、とりあえずロスの友人宅へ身を寄せねばなりません”)。時間の無駄ですので、もし私に興味がないのなら“ノー”といって下さい」
「ミスター・ヨシロー、あなたはこの国では無名ですが、エキゾチックなショウのアイデアには興味を持っているのですよ。今夜あなたのレコードをゆっくり聴いて、考えてみたいのです」
「聴かないで下さい(あわてる)。レコードだけで評価されたら、この国の歌手にはかないませんから(本音である)。でも今夜オーディションのつもりで歌わせて下さい。客の反応を見れば、あなたはきっと気に入ると思います。私のショウはウ二コ(ユニーク)ですよ」
カラカスの新聞でウ二コということばで賞められた私は、以来のバカのひとつ覚えのようにウニコを連発していたのだが、のちメヒコでのデビューの日、着物の早変りの手順を間違えて大失態をしでかした時みんなから「本当にユニークですね」と心をこめて?いわれたものだった。
ところで、オーディションと言えども無料で客の前で歌うことは、他の歌手にとっても営業妨害となる。だからこの国ではいかなる場合でも歌手が無料出演することをユニオンが禁じている。そんなことを説明したオーナーは
「どうです、今のバンドのリハーサルが終わったばかりなので、この場でオーディションをしては?」
と言う。
「でも今は楽譜も衣裳もホテルにあります。第一、客がいないのはやりにくい」
「バンドは楽譜なしでなんでもなんとかつけてくれます。衣裳はあなたの写真を見ながら想像しましょう」
開店前で忙しいボーイさんやコックたちを客席にすわらせ、オーナーは帰り仕度のバンドを呼びとめたが、なんとこれはマリアッチではないか。これでは長唄の囃子でジャズとまで言わなくてもチグハグなものだ、なにしろ私のショウのオープニングはラテン・ロック風にアレンジした「ソーラン節」なのだから。
「ええ、ままよ!」
と決心、楽譜なしの打合わせで生れ出たその前奏はどこか中国風、バイオリンの音色が胡弓のそれに似ているためだ。
「みなさん「ラ・バンバ」の感じのイントロでいいんですよ」
と注文して再び前奏が始まったが、我慢の限界ぎりぎりの感じ。ドラムスがないのでバイオリンの胴の裏を弓で叩いてもらい「ア、ドコイチョ、ドコイチョ!」
としか聞こえないかけ声も入れてもらって、ひきつりそうになる顔に無理に笑みを浮かべ、私は「ソーラン節」をやっと歌い終えた。この三分間の長かったことと言ったら!しらけると悪い--------もっとも始めからどっちらけだったが---------ので終わるとすぐに
「ハイ、ここで拍手がきまーす」
とボーイやコックさんを促す。つられてオーナーもパチパチと手を叩いたが「それのどこが面白いのかね」
と言いたげな顔をしている。考える隙を与えまいと私はすかさず
「すぐ二曲目のイントロに入り、ライトが七秒間消えると仮定して下さい。そのわずかな間に着物の早変り、ライトが再びつくとお客さんは驚くのです。ほらそこにある写真の、白っぽい着物から黒いのに七秒で変えるのです。もち論その間にバックライトの音楽はストップなし」
と説明するが、オーナーには早変りの意味が分からぬ様子なら、バンドは一向に次ぎの曲に入らない。だから二曲目「フラメンコ・ロック」は自分でイントロも間奏も、おカズ(歌の切れ目に入るバックの音)も、「デケデケドンドン」と自分の口で歌い、ついでにエンディングもバンドにあてつけがましくもヒステリックに「ジャーン」とやる。
義理の拍手のかわりにみんな笑ったのが、かえって救いであったが、ピエロの役はもう沢山、次の曲をやる勇気はもうなかった。
「いいバンドでちゃんとリハーサルをやればムイ(とても、ベリー)・ナイス----------当時のメヒコの若者たちの流行語だった-------------------・ショウをお見せ出来たのに、残念なことです」
と私は弁解した。けれど、このオーナーが私のことを忘れてくれない限り、このお店から声がかかることなどあり得ないと思ったことだった。
十日あまりの滞在で金を使い果たした私は、とりあえずロスアンジェルスの友人宅へ身を寄せるべく旅発った。六月十日夜半である。この間売込みに奔走し「今後の努力も惜しまぬ」といってくれたグスタボに、出発間際私の心変わりを伝えねばならかった時は、胸が痛んだ。世間知らずだった私は、十日間もかかって契約のひとつも取れなかったのは彼の責任と思いこんでいたし、その前日、新しい二人の人物を識って気持ちがぐらついたのである。
一人は一九二〇年代にかけ、故ペドロ・インファンからパンチョス、マリア・ビクトリアに至るまで数多くのスターを世に送り出したチャト・ゲーラ老、他の一人は闘牛士あがりのダンディなマネージャー、マノロ氏である。
多少運が悪くても、二人の内どちらかがロスで待つ私に吉報を送ってきくれるだろう。それは一週間先とも。ずっとずっと先のことのようにも思えた・・・・・